いまこそ冷静に、急成長した日本株市場の状況を見きわめよう
日本株は今年(2025年)、米国株を上回る上昇を記録しています。高市政権の誕生により積極財政への期待が高まったことに加えて、いわゆる「AI(人工知能)相場」の影響も否めません。株価上昇が限られたAI関連銘柄に偏る一方で、有望銘柄が割安になっているケースもあります。冷静に日本株市場の状況を見きわめることが重要です。
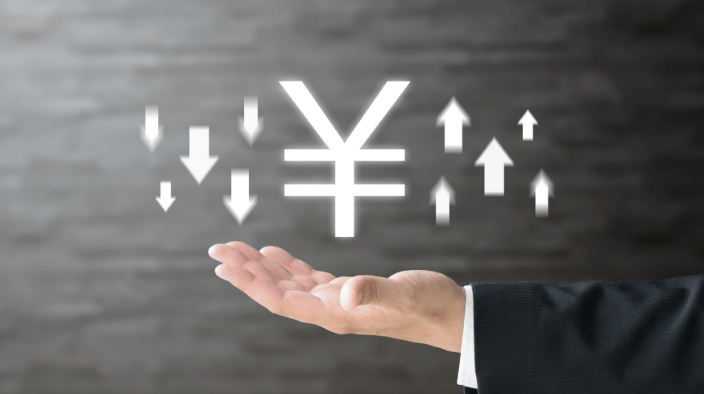
Q.日本株が今年、急激に上昇したのはなぜですか。
日経平均株価は25年11月17日時点で5万323円91銭となり、24年末の3万9894円54銭から、今年はここまで26.1%の上昇を記録しています。同期間中の上昇率を比較すると、米国のダウ工業株30種平均は9.5%、S&P500種株価指数は13.4%となっており、日経平均株価の大きな値上がりが目立ちます(いずれも終値ベース、以下同様)。
なかでも注目したいのは、直近半年ほどの上昇率がきわめて高いことです。実は今年4月7日時点で、日経平均株価は年初来安値の3万1136円58銭まで下落していました。トランプ関税ショックの影響によるものですが、そこから上昇に転じ、10月31日には終値として史上最高値となる5万2411円34銭まで駆け上っています。
その間の上昇率を月平均で見ると10%を超えており、過去に市場の心理が一変して上昇が続いた局面と比較しても、非常に高いことが分かります。例えば新型コロナウイルス拡大後の急反発局面にあたる「2020年3月~21年2月」は、月平均5%でした。ブラックマンデー後の底入れからバブルのピークに至る「1987年11月~89年12月」でも、月平均3%に過ぎません。
今回の急激な株価上昇の背景として、大きく2つの要因が考えられます。ひとつは今年10月4日に高市早苗氏が自民党の新総裁に選出され、同21日には日本初の女性首相に就任したこと。高市氏はかねて積極的な財政政策と金融緩和志向で知られており、首相就任にあたって「強い経済」の実現を掲げ、財政拡張や防衛支出拡大の重要性を唱えています。
高市政権の誕生にとりわけ強く反応したのが海外投資家です。東京証券取引所が発表した投資部門別株式売買動向(東証と名古屋証券取引所の合計)によると、海外投資家は10月に日本株を3兆4413億円買い越しました。月間ベースで過去最高だったアベノミクス相場下の2013年4月(2兆6826億円)を大幅に上回っています。
もうひとつの要因は、昨今の米国株高を主導している「AI相場」の影響です。米国ではダウ工業株30種平均が11月12日に、S&P500種株価指数とナスダック総合指数が10月下旬に、いずれも終値として史上最高値を付けました。
9月には半導体大手のエヌビディアが、生成AI「ChatGPT」を開発する米オープンAIに対して最大1000億ドル(約15兆円)にのぼる出資を公表するなど、米巨大テック企業を中心にAIインフラへの巨額投資が加速しています。AI関連需要の増加期待が高まることで米国株が上昇し、それが日本のAI関連銘柄にも連鎖して株価上昇を招いたわけです。
AI相場で割安になった有望銘柄を購入するチャンス?
AI相場の特徴は、一部の限られた銘柄が株価上昇の大きな部分を担っている点にあります。日経平均株価は24年末から今年10月末の史上最高値まで1万2516円上昇しましたが、その寄与度の7割はソフトバンクグループ(SBG)、アドバンテスト、東京エレクトロンのAI関連3銘柄で占められていました。
24年末~今年11月17日の期間で株価の上昇率を見ると、SBGが121.4%、アドバンテストが117.4%、東京エレクトロンが37.6%となっています。一方で、高収益銘柄として知られるキーエンスの株価は同期間に15.0%下落しており、日経平均株価に対しても出遅れが顕著です。
2025年3月期の営業利益率はキーエンスが52%で、SBGの10%やアドバンテストの29%をはるかに凌ぎます。ROE(自己資本利益率)もキーエンスは13.5%となっており、9%程度が平均の日本株においては申し分のない水準といえます。それでもキーエンスが置き去りにされる理由として、市場関係者の間では「バンドワゴン効果」の働きが指摘されています。
バンドワゴン効果とは、多数の人が支持している物事に対して、よりいっそう支持が大きくなる現象のことで、勝ち馬に乗ろうとする集団心理を指します。すなわち今年の日本株市場では、利益率やROEといった経営の質を示す指標よりも、表面的な人気で銘柄が選ばれる傾向が強くなっているのです。
AI相場については、ここにきて懐疑的な見方も広がってきました。オープンAIはエヌビディアなどとの間でいわゆる「循環取引」を繰り返しており、市場ではそれが2000年前後のIT(情報技術)バブル期を彷彿させると危惧されています。11月初旬には米ゴールドマン・サックスなどの金融機関トップから、AI相場の過熱感を指摘する声が相次ぎました。
AI関連の過剰投資に対する懸念が強まる一方で、市場支配力や製品の競争力などを踏まえた利益率の高さを考えれば、企業がAIへの投資を加速させるのは当然という見方もあります。いずれにしても今後、AIの普及が社会をどのように変えていくのか、さらには利用者がAIサービスを有料でも使いたいと思う「実需」がどれほどあるのか、まだ誰にも分かっていないのが現実です。
私たち個人投資家にとって大切なのは、急成長した日本株市場の状況を冷静に見きわめ、できる限り効率的な運用を心がけることではないでしょうか。AIの将来性がどうであれ、期待先行のAI相場によって現在の株式市場に大きな「偏り」が生じているのは事実なのですから。
例えば前述したキーエンスやリクルートホールディングスのように、市場で「高クオリティー」と目されている銘柄がAI相場の影響で割安になっているとしたら、購入もしくは買い増しのチャンスと言えるでしょう。個人投資家は機関投資家と違って、1年程度の短期間で市場平均を上回る運用成績を求められるようなことはありません。その利点を、いまこそ最大限に生かすべきだと思います。(チームENGINE 代表・小島淳)