上値追い予想も、残る脆弱性=日本経済と株式市場の今後
第390回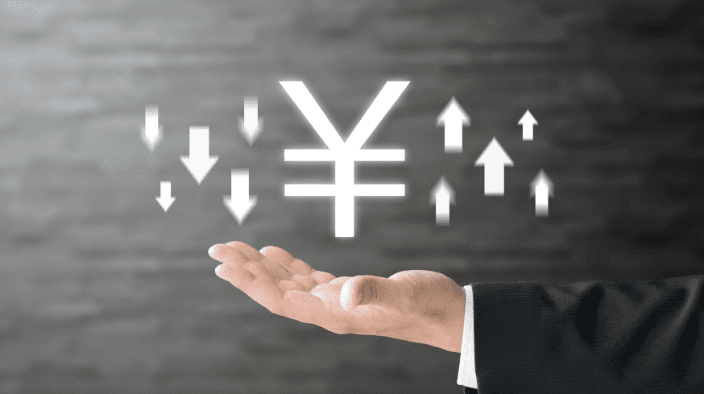
前回が「米経済と株式市場の今後」だったから、今回は「日本経済とその株式市場」にも関心を集める。日本経済では一部企業の収益力が上がるなかで、株式市場では連続した高値追い現象などかなり大きな動きも見える。このコラムをお読みの方も、日本の株に強い関心をもっておられる方が多いと思う。なんと言っても母国市場だ。
日本人はほっておけばやはり「円資産」中心の生活だ。給与、支払いなど日常的な資金のやり取りも大部分は円貨決済だ。意図をもってかなり外貨部分を増やしたにしても、円貨は多くの日本人にとって常に身の周りにあるお金であり重要だ。筆者は「世界の株式市場の流れを決めているのは米国市場」との考え方から、どちらかというと米国市場の動向・その分析を中心に取り上げてきたが、今回は母国市場の展望を取り上げる。
日経ヴェリタスのテレビ番組である日経ヴェリタストークにはもう長い間1月余に1回程度の頻度で出演しているが、たまたま2025年10月14日の放送は「それでも買える日本株 日経平均10万円へのロングラリー 高市トレードの先①」という記事を番組として取り上げた。「日経平均10万円」という刺激的なタイトルのように、出演していてとても興味深い番組内容だった。
実は私は日本株の先行きに関して、この記事に登場する「2029年に10万円」といった方々の強気論には「乗れないかな」と思っている。「年内に5万円」「それは通過点で、数年以内に6万、7万」との見方には賛成する。そういう範囲内での「日本株強気論者」だ。しかし何が起きるかなかなか読み切れない時代に2030年とかを予測するのは「一種の想像的感想戦」だと思っていて、あまりリアリティがない議論のような気もする。
むろん「投資は長期」が原則で、長い視点でマーケットを見ることは必要だ。しかしあまりそこに拘泥してもしょうがないと思っている。為替相場と長く付き合っている筆者の肌感覚で言うと、「3カ月先はかなりの程度予想できる。しかし一年以上先の事は正確には分からない」というのが正直なところだ。しかし繰り返すが、自分の人生設計の中で「長期的視点からの投資計画」は重要だ。
強気論多し
私がこの記事を読んで最初に感じたのは、「結構強気の人が多いんだ」ということだ。これは番組でも申し上げた。ヴェリタス記者の記事への取り組みは、公明党が連立政権離脱を自民党に通告した10月11日以前からだが、記者は公明党離脱後も追加取材をしている。だから今の政治の混乱劇の最初の部分を織り込んでいる。
それでも強気論が多いということは、今の業界の空気を反映していると思う。記事にもあるが、話題に上ったのは「日経平均は2029年に10万円に到達してもおかしくない」との見方。この予想をした方は、「高市総裁は英国のサッチャー元首相を想起させる人物」だとして、サッチャー氏の在任期間中に英国のGDP(国内総生産)が3.4倍に、株価が6倍に上昇した」ことを引き合いに、日本株上昇のストーリーを想定。
その他にも「2030年に10万円」との予想も掲載された。この予想をされた方は、「(10万円到達は)従来は34年を想定していたが、高市総裁をみて前倒しした」と述べたという。記事によれば、ヴェリタスが取材した専門家の間では、10万円には至らずとも「今後数年で6〜7万円」を目指せるとの声が多かったという。
冒頭にも触れたが、実は筆者もこの見方だ。私も年内に日経平均は5万円の水準を一度は上回ると見ていて、その後の年末にはその水準を下回るかもしれないが、来年、再来年と基調は強いと考えている。筆者が基本的に日本の株価の先行きに強気なのは、
- ① 市場で注目を集めるような日本企業はかなり競争力があり、業績の見せ方などが世界レベルに達しつつあり、世界の中でも常に注目される存在となっている
- ② 日本企業の株価水準は依然として世界のレベルから見れば出遅れていて、世界の投資家の日本株への関心は強く残っている
- ③ 長く続いたデフレ的環境下での「値上げを行うことの困難性」を脱し、日本企業が比較的容易に、かつ合理的に値上げを浸透させることが出来るようになり、ビジネス環境が改善した
高値追いも、伸びにはラグも
しかし筆者は、「30年に10万円の日経平均」といった見方に俄には与みできない。いくつか理由がある。やはり日本には世界の投資市場に出しても燦然と輝く銘柄が少ないと思う。世界に伍(ご)していける日本企業はむろんある。しかしそれらは、世界の特定産業における大きな塊として「世界をリードしている」わけではない。個々の企業として優秀というレベルだ。依然として独特の孤立感がある。世界の多くの投資家に「魅力的な日本の企業群」と映るかについては疑問が残る。
かつ日本が国としてラテン語系列とは違う言語(日本語)を持ち、訪問しようにも意を決しないといけないような遠方(極東)に存在するというのも、世界の投資家がどちらかというと日本企業を優先的には考えない原因だと思う。バフェット氏のように見抜いている人はいるが、まだ少数派だ。
日本株ブームは今までに何回もおきたが、筆者の印象だと世界の多くの投資家は、日本といってすぐに思い出す銘柄はあまり多くないようだ。日本株ブームが起きると最初に買われるのはトヨタだった。「日本=トヨタ」と思っている人が多い印象だった。「日本のことをあまり知らない」海外の投資家の資金が、まず日本の特定有名企業に集まった。そういう意味では、日本企業・日本市場は世界の投資家が一歩を踏み出すのに、やはり手間かかる市場・国なのだ。ただしAIの時代に、それは徐々に解消されつつある。
日本経済が抱えている問題も多い。「高市総裁は英国のサッチャー元首相を想起させる人物」で「サッチャー氏の在任期間中に英国のGDPが3.4倍に、株価が6倍に上昇した」ことを日本株に強気になれる理由として挙げている人もいた。しかし今の日本の政治情勢はとても不安定だ。「高市さんが自民党総裁からさらに総理大臣」になるには力業が必要だし、「高市首相」の政策発動余地が当時のサッチャー首相ほどに大きいかと言えばそうではない。
日本は安倍さんの時代から「GDP600兆」が大きな目標だった。しかしデフレ傾向から抜け出すのに時間を要する中で、名目GDPで日本経済が600兆の規模に達したのは2024年になってからだ。世界でどの程度のスタンディングかというと、ドル・ベースではドイツに抜かれて「世界第4位の経済規模」にとどまっている。
筆者は日本がGDPを増大させるペースは遅いと考えている。少子化・人口減少も進む。「在任期間中に英国のGDPが3.4倍」といったことは、日本では起きないだろう。ちなみにサッチャー元英国首相の任期は1979年から1990年と長く、その間英国の政治は安定していた。高市首相が誕生しても政権基盤は弱い。長期政権は無理だ。
相対的優位は米国
投資家が「投資先」を考える上でやはり重要なのは、「相対的優位」だ。投資はどうせやるのなら、「安全な果実(値上がり益、配当益など)」がより多く収穫できる場所がいい。日本(日本株)にチャンスがあることは分かっていても、「もっと有利なマーケットはないのか」という問題意識を持つことは重要だ。いつの時代にも、ある程度の「投資先分散化」は必要だ。円が一方的に価値を高くする時代はもうとっくに終わっている。今後はむしろ円安が基調だろう。外貨投資の必要性は高まっている。
投資は世界が舞台だ。投資家は常に今の世界を広く見て、収益性が高くキャピタル・ゲインが狙える場所を見付けるのが良いと思う。筆者が真っ先に考えるのは米国だ。それはここのコラムでもずっと述べてきた。大統領にはいろいろと問題があるが、あえて言えば彼が引き起こす様々な問題が米国経済の可能性を拡大している面もある。
何せ彼は、ホワイトハウスの集計だけで「5.1兆ドル」という大規模な対米国投資を各国に約束させている。加えて米国は自国産物・製品の各国向け輸出を強力に後押し。貿易赤字削減の努力をしているわけで、米中摩擦のコアは今は「大豆」になっている。中国が今年5月以降米国から大豆を全く輸入していないことが背景。
「投資先の安全性」は、しばしば投資効率よりも重要だ。投資が接収されるようでは話にならないし、理由も希薄な税金を課されるのは問題だ。そういう面(資産の安全性を担保する法的枠組み・国家の安全保障環境など)から世界を見渡すと、日本人投資家にとって「安全な投資先」は実はそれほど多くはない。米国、イギリス・ドイツなど欧州の一部の国。いずれも大きな、流動性の高いマーケットとその商品構成を誇る。
その中から「どの国が最適か」を考えるのは、個々の投資家の責任であり、醍醐味でもある。インドも面白いかもしれない。投資のかなりの部分を日本に残しつつ、世界で可能性を探るのは、今後日本の投資家にとってとても重要な事になる。時代は常に変化していてその都度考え方を変える必要があるが、筆者の今の推しは「日本株+米国株+少々のインド株」かな。