“パウエル語”の「そもそも」的読み方
第387回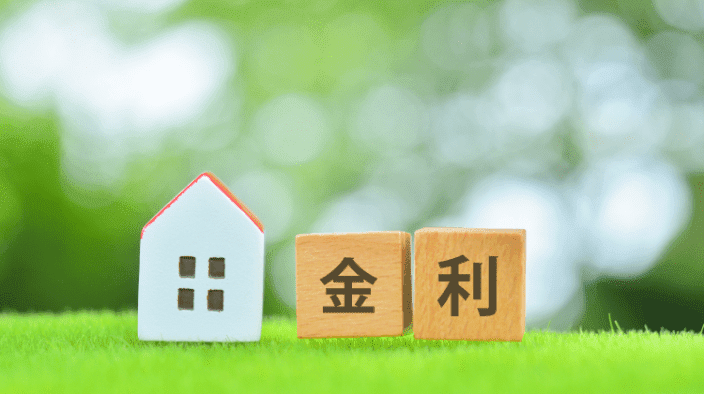
秋以降の金融市場を予測する中で、「中央銀行の出方」が改めて注目を集めている。米国では「利下げ」とそのペースが焦点だし、日本では「利上げ」が大きな関心事。世界の主要中央銀行の政策ベクトルが「逆を向く」というのは、世界経済の一体化が進んだ中ではなかなかない事態。おそらくマーケットへの影響もある。
トランプ米政権の発足と各国への「相互関税」の発動に伴い、世界の中央銀行は予測しがたい物価・景気情勢の変化に直面している。舵取(かじと)りは難しい。「トランプ相互関税」そのものが、一審に続き控訴審でも「大部分は合法ではない。関税を決める権限は基本的に議会にある」との判断が下された。土台そのものが怪しくなった。着地点は見えない。トランプ米政権は最高裁に上告する意向。
中央銀行の政策運営が難しいのは「全てが判明するまで待つ」ということが出来ない事だ。物価や雇用情勢は常に変動している。関税とは別の要因も多い。その都度対応が必要だ。世界の中銀の中でも、最も注目されるのはFRB(米連邦準備理事会)の動き。母体の米国経済は世界最大。覇権国でもある。
今回は、その米国の中銀議長の発言を、どう読み解けば良いのかに焦点を当てる。見出しで「パウエル語」と表現したのは、今のFRB議長がたまたま同氏だからで、それは「グリーンスパン語」でも「バーナンキやイエレン語」でも良い。彼等の言葉・発信をどう読み取るべきか。
8月のジャクソン・ホール会合での同議長の発言については、世界のマスコミの受け取り方と、マーケットの理解が大きく乖離(かいり)した。なぜそういう事が起きるのか。それを今回整理したい。長くマーケットと付き合い、中銀トップの発言をフォローし続けた筆者としての見方を述べたい。
長い読み取り歴
筆者の「中銀総裁発言の読み取り歴」は非常に長い。自分でも笑えるくらいだ。ニューヨークに居た頃から始まっていて、かれこれ40年にはなる。ずっと市場周りの仕事をしていたので、常にマーケットに大きな影響を及ぼす中銀トップの発言をフォローし続けている。「これ重要」と思うポイントは以下の通り。
- ①国の経済を動かす立場の人なので、基本的に彼等の発言はいつも慎重だ
- ②「万が一」の事も想定して、発言に様々な逃げ場を設け、間接話法、普段使わない単語も駆使
- ③重要なのは常日頃、中銀トップの講演・発言をトレースし、発言履歴を頭に入れておくこと
- ④毎回出てくる表現には気を払わなくて良い。「新しい単語、表現」にこそ意味が込められている
今年のジャクソン・ホールでの(パウエル議長の講演)は、トランプ米大統領のFRB、同議長攻撃が熾烈で、執拗に「利下げ」を迫る状況下。特に注目された。この講演に限らず、FRB議長の講演は予定時間ピッタリにFRBのHPにアップされ、しばしば動画が配信される。今回も筆者はそれを見た。
リンク先を見ていただければ良いが、彼の講演タイトルは「Monetary Policy and the Fed’s Framework Review」。一目で「2つのテーマを取り扱う」と分かる。うち重要なのはむろん「Monetary Policy」の部分だ。フレームワークの話はあとでゆっくり読めば良い。講演分量が2つのテーマに2分されているということは、全体の半分前後に重要な金融政策的「結論」があると予想できる。
中銀の総裁は普段、講演の冒頭で「結論」めいたことを言うことはない。金融政策を司るトップなので「結論的まとめ」に至るまでに、「そこに至る論理」や「その前提」をすべて提示する。その後に「まとめ」を示す。筆者は目星を付けて、「Evolution of Monetary Policy Framework」という後半の話題のタイトルの前の数パラグラフに目を凝らした。
目に入ったのは、「Monetary policy is not on a preset course」の部分だ。この文章は、特定のスタンスを提示した後に、「事前に決められた政策運営ルートはない」ので「今はこう言ったが、どうなるかは分かりませんよ」と現実の複雑さをリマインドする為のもの。特にパウエル氏が良く使う表現だ。
市場は肝に直行
ということは、その直前に彼が一番言いたいことを言っている可能性が強い。目に付いたのは「Nonetheless, with policy in restrictive territory, the baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance.」という部分だ。「Putting the pieces together」で始まるこのパラグラフは一目で「私の今日の結論提示」と判断できるもの。
2つの文章の間には「今はチャレンジングな状況」と言いながらも、「政策金利の水準が1年前に比べて中立金利に100BP接近しており(緩和は一定程度進んでいるとの理解)、失業率と他の労働市場指標は安定しているので、政策スタンスの変更を考えるに当たっては、事を慎重に進めることもできる」としている。これを読んだ記者は、「あ、FRBはまだ利下げに慎重なのだ」と読むかもしれない。
しかし重要なのはその後だ。直後に「Nonetheless, with policy in restrictive territory, the baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance.」という文章を置いている。訳せば「しかしながら、現在の米国の金融政策が引き締め領域にある中で、基調的見通しと、リスクバランス変化は、政策スタンス調整を正当化するかもしれない」と述べている。
中銀総裁の言葉使いは微妙だ。時に分かりにくい。adjustingは「調整する」で、この単語だけではどの方向を向いているかは不明。そこがパウエル(中銀使用)語の肝だ。「引き上げ」とか「引き下げ」とかの直接的な単語は使わない。しかしこの文章の前にある「with policy in restrictive territory」(現在の政策は引き締め領域)から、議長の念頭にあるのは「引き下げ調整」なんだと分かる。
ポイントは、事前に市場がどちらの可能性を念頭に置いているかだ。「雇用情勢が悪い」「FRBはいつ動くだろう」と皆が思っている時期なので「may warrant adjusting our policy stance」を市場は直ちに「パウエル議長は利下げを示唆」と受け取った。実際にこのパウエル議長のジャクソン・ホール発言を受けてニューヨークの株価は大きく上昇した。
しかし一方で、同じパウエル講演を読んだ記者の中には「議長はまだ利下げには慎重」という印象を強く持った人もいた。そしてその方向(理解)で記事を書いた。普段あまり議長の講演を読み慣れていない経済記者などは、今回のパウエル講演を見て「やっぱり議長は慎重だ」と思っても不思議ではない。なぜならいつも通り「慎重さ」を窺(うかが)わせる単語はあちこちに鏤められているので。
それはいつものこと。マーケット・エコノミストは「変更点はここ」とばかりにポイントを押さえ、トレーダーはそれを材料として直ぐに動く。マーケットにとってはタイミングが全て。他の人より機敏に動かねば勝てない。実に素早い。筆者はそれをずっと見てきた。なので、中銀総裁(今はパウエル氏)講演の読み方は速くなった。
しかし解説記事と市況記事で異なる方向性の記事が載ると、読者は「一体どっち」と思うかもしれない。今回もそういう局面だった。しかし筆者は「マーケットがどう理解するか」が重要だと思っているし、中央銀行の総裁もマーケットに向かって語っている面があるので、「市場の視点」がいつでも重要だと思う。
利下げ後はペースダウンも
パウエル議長のジャクソン・ホール発言を起点に「FRBは9月にも利下げ」がマーケットの一般的受け止め方となっている。その後も色々経済指標は出てきているが、総じて雇用には不安感がある。なので、9月の「利下げ」は8割方の市場関係者のコンセンサスだ。
むろん、そんなコンセンサスでもいつでも変わりうる。とんでもない事件が生じたり、予想外の経済指標が発表になるケースもある。各種ポイント(購買の際などに付与)やデジタル化決済など経済活動は複雑化しているので、昔ながらの経済統計の正確性はかなり毀損されている。
比較的早期に、予想通りの米国の利下げがあったとする。下げ幅は恐らく0.25%。実は問題は「その後」だ。連続利下げを見る向きもある。今のところ「関税引き上げ」による物価上昇の幅はそもそも小さいし、あったとしても一時的というトランプ米政権の主張が正統性を持っているように見える。
しかし関税起因の価格上昇による消費者離れを警戒し、当初は自腹を切り利益を削っていた輸出や米国内販売業者も、秋頃から徐々に環境を見ながら「値上げ」に打って出るとの見方もある。マーケット調査に当たっている多くの研究機関がそうリポートしている。筆者はその可能性が高いと見ている。
難しいのは、短期金利を引き下げれば長期金利も下がるというものではない点だ。インフレ懸念が残っている時に急ぎ利下げをしてしまうと、「将来のインフレ」が予想されて長期金利が上がってしまうことがある。最近のニューヨークの市場でもそうした状況が見られた。政策金利を下げても、様々な貸出に適用の長期金利が上がってしまうなら、それは逆効果だ。
そもそも、今の世界では長期金利は上がる傾向にある。9月4日の日経新聞9面には「政治混乱 超長期債離れ」という記事がある。長期債離れということは、長期金利が上がるということだ。この記事には「市場参加者の多くは政治が財政悪化に歯止めをかけられない状況に強い危機感を持つ」という指摘がある。つまり経済に影響を与える長期金利には、世界的に上昇バイアスがかかっているということだ。ということは、安易な利下げの継続は実は難しい。
筆者は秋の利下げ後の金利調整が足早だとは思っていない。既に米国の30年債金利は5%に一時乗ったりしている。トランプ米政権が利下げを急げば急ぐほど、実は「長期金利が上がってしまう」というパラドックスの危険性がある。
金融政策の舵取りは実に難しい。短期金利を下げれば経済がすべてうまくいくといった単純なものではない。多分トランプ米大統領は基本的に不動産業者だから、「低金利」が好きなのだろう。しかし経済全体を見ればそう簡単ではない。