株高を享受するドイツ、経済の強さ回復が課題
第384回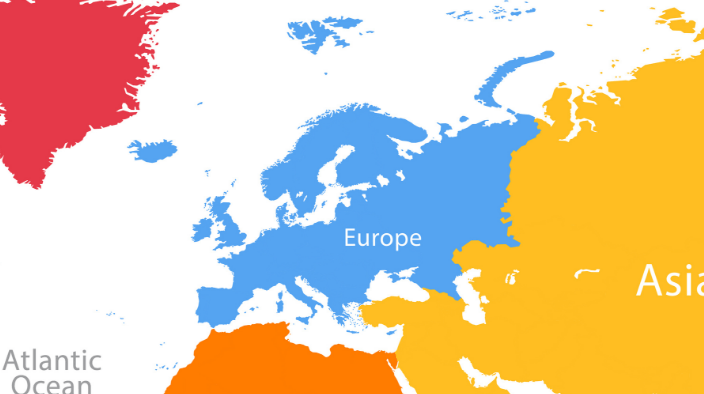
今回は久しぶりに目を欧州に転じる。しばらく取り上げないうちにドイツを中心に政治・経済の両面で深い構造変化が生じ、それが世界を巡回するマネーの大きな受け皿を形成。欧州主要国の株価が強い上昇トレンドの中にあるからだ。日本の投資家としても、欧州で生じている変化に理解を深めておくことには価値があるだろう。
「世界の株価はもっぱら日米を中心に見ている」という方は、とにかく手元のデバイス(PCやiPhoneなどのスマホ)で、ドイツの代表的株価指数であるDAXの動きを見て欲しい。期間は1年でも2年でも良い。その右肩上がりに改めて驚くだろう。加えて言うと、この間のユーロと円との為替相場はユーロ高・円安トレンド。ということは、1年なり2年前に円資金をユーロに転換して欧州の株を買った人がいたら、その人は大きな収穫を得ているに違いない。
もっとも一、二年前に日本から欧州への投資を簡単に決断出来たかというと、実はなかなか難しかった。当時米国株は魅力的だった。「投資は身近で情報が多い日本、米国がやはりいい」と考える人が多かったのではないか。当時欧州はといえば、ロシアがウクライナに攻め込んで、かつ占領地域を徐々に拡大している最中だった。どうしても「欧州は戦争地域」との印象が拭えなかった。
もっと重要なのは、極右政党の台頭などで欧州には政治的にも混乱した印象があり、経済的にも安かったロシア産エネルギーからの切り替えに苦悩し、低成長・失業増加などの苦境があることが伝えられていた。しかし「人の行く裏に道あり花の山」の市場格言通り、その当時に対欧州投資を決断した人には、今は大きなリワードがもたらされているのだ。
ドイツ経済の現状
そこに日本の投資家として何か油断があったのか。筆者は「あった」と自分を含めて思っている。欧州主要国ドイツについては、我々がかつて知っていた国ではもうなくなった。「大きく変わった」し、「その流れは今後しばらく続く」と思う。欧州に関して、頭の中のイメージを一新する必要がある。残っている「メルケルのドイツ」は過去の残像だ。今は「新CDU(キリスト教民主同盟)党首メルツのドイツ」であり、そこには「戦後のイメージ」を払拭し、それからは大きく変容したドイツがある。「変わったドイツ」を生み出したのは、遠因を辿(たど)ればロシアのウクライナ侵攻だ。
政治的変化
戦後のドイツを主導してきた中道政党(CDU・CSUや社民党)は、依然としてドイツ政治の主流を形成している。しかし「ドイツのための選択肢」(略称:AfD)などの政治集団が大きく勢力を伸ばしている。それらは極右政党と呼ばれ、今のメルツ首相率いる中道政権も新勢力の存在を念頭に置かざるを得ない状況だ。ドイツを巡る政治環境は大きく変わった。
変わる財政政策
変化の中でも重要なのは、ドイツが「積極財政の国」になったということだ。同国はメルケル首相(2005年11月から2021年12月)の在任期間中、一貫して「赤字を極端に嫌う緊縮財政政策」の国だった。財政赤字嫌いは顕著だった。当時GDPに対して財政赤字の規模が膨らみ、国債発行に依存する傾向を強めた日本とよく比べられたものだ。ともに敗戦国だが、その進路はあまりにも違った。国防費の伸びにも大きな制約を課してきた。それはナチス時代への反省から来たもので、法的枠組みがあった。
その枠組みとは、基本法115条を指す。「連邦政府の財政赤字はGDPの0.35%以内に制限する」という「債務ブレーキ規定」。2009年に導入された。しかし2025年3月に債務ブレーキの対象を一部緩和する基本法改正案が可決された。つまり今年の春という直近だ。「一部対象」とは具体的に防衛費。GDPの1%を超えるレベルまで引き上げられ、また州政府の財政規律も一部緩和された。これはドイツにとって大きな方向転換だったし、マーケットのドイツ観を大きく変えた。
その大きな契機は、「ロシアが引き起こしたウクライナでの戦争」だった。同国支援で膨大な軍事・財政支援が必要となった。また米国の第2次トランプ政権は、欧州北部での戦争により大きく関与するよう欧州に圧力をかけた。「ナチス時代への反省」から生まれた戦後ドイツの緊縮財政政策の転換は、今でも大きな議論を呼んでいる。しかし既に大きな方向転換がなされたと考える。
上がる株価―構造変化が背景
このドイツの顕著な方向転換は、目ざとい世界の一部投資家の関心を集めた。欧州で経済規模が大きく、マーケットも深い国の大きな政策変化だったからだ。ドイツ経済が置かれている状況(現況)を差し置いても、資金の移動先として選ばれた。米国がトランプ関税導入で市場が動揺する中で、「米国以外の投資先」が必要だったからだ。
「ドイツ経済の苦しい現状とDAXに象徴される株価の上昇には乖離(かいり)がある」とよく指摘される。しかし世界の投資家が見たのは経済の状況ではなく「財政政策まで変えて国の形を変えようとしているドイツの将来」の方だった。改めてドイツ経済の数字を見る。状況は現状苦しいままだ。
ドイツ連邦銀行のナーゲル総裁は今年春、ドイツ経済が2025年に「小幅な景気後退(リセッション)」となる可能性があると述べた。そうなればドイツにとって初めて3年連続のマイナス成長となる。ドイツ政府は既に今年の同国成長率予想を0.3%からゼロに下方修正している。
ドイツ経済が抱える構造的問題は以下の点だ。
- ①安いロシア産のエネルギーを頼っていたが、ウクライナ戦争の勃発によってそれへの依存引き下げを余儀なくされている。その結果製造コストが上昇し、競争力低下が起きている
- ②メルケル氏の頃のドイツは一貫して中国需要を取り込む戦略をとっていた。しかし米国の対中姿勢強硬化もあり中国依存を低下させており、有力な輸出市場の喪失に悩まされている
- ③フォルクスワーゲンがドイツ国内の一部工場の閉鎖を発表するなど、産業構造の転換(EV化や脱炭素)で他の諸国との競争に負けた
- ④従来強かった自動車など製造業の縮小で、中堅企業を中心にリストラや工場閉鎖が進行、また若年層の離職増加、高齢化の加速、熟練労働者不足など労働市場の構造的な課題も顕現化
こうしたドイツ経済の厳しい環境が伝わってきていただけに、日本の投資家がドイツやその周辺の国に対する投資に二の足を踏んでいたのには十分な理由がある。しかし日本の投資家が足踏みしている間に、株価は静かに、しかも大きく上昇した。それを過去データの推移線であるチャートが示している。
日本の投資家としての考え方
金融商品も数多く、慣れ親しんだ対米投資に比して、欧州への投資にはやはり「距離がある」と筆者も思う。しかし株価は米国を凌ぐ勢いで上がってきた。今後どのような姿勢で臨むべきか。今まで日本と米国を主な関心対象としてきた筆者にとっても、これは大きな問題だ。同じ問題意識を持っている日本の投資家の方も多いと思う。
結論から言うと、今まで以上に自分の投資対象として欧州を強く意識した方が良い時代が来ていると思う。既に挙げた構造問題は深刻だが、ドイツ経済をとってもいくつかの明るい材料が出てきている。一部の経済指標では個人消費の持ち直しの兆候が見られるし、先に指摘した2025年3月に議会が認めた拡張的な財政政策は、今後景気を下支え、刺激するかもしれない。特に防衛費拡大の流れの中で、軍事を担うドイツの企業には資金が集まっている。
確かに欧州は複雑。国の数が多くて、一つ一つの国の経済規模・市場の大きさは米国と比べると小さい。ドイツにしてもGDPで日本を抜いて世界第三位といっても米国経済の数分の一だ。マーケットの規模も流動性も米国市場の比ではなく脆弱だ。我々がよく知る投資対象となる銘柄数も少ない。しかし今後は我々が選べる欧州対象の金融商品は増えるだろう。
ユーロという一つの大きな塊としての通貨を持ち、「ドル以外にどこに投資」という問題が起きたときにすぐ頭に浮かぶのは同通貨だ。今後も選択肢として大きいし、欧州経済や企業が力強さを増やせばなおさらだ。筆者としても今後欧州市場への関心を高めていきたいし、このコーナーでもより回数多く取り上げたい。
— — — — — — — — — — — — — — —
この原稿を書いている最中に日米の関税交渉妥結が報じられた。次の原稿ではEU(欧州連合)との交渉結果も出ていると思うので、米国の対中関税交渉の結果も含めて取り上げたい。米国のトランプ政権は、金融市場の混乱が怖いのか、マーケットの想定内にやはり柔軟に対応している印象がある。次回に詳しく取り上げる。